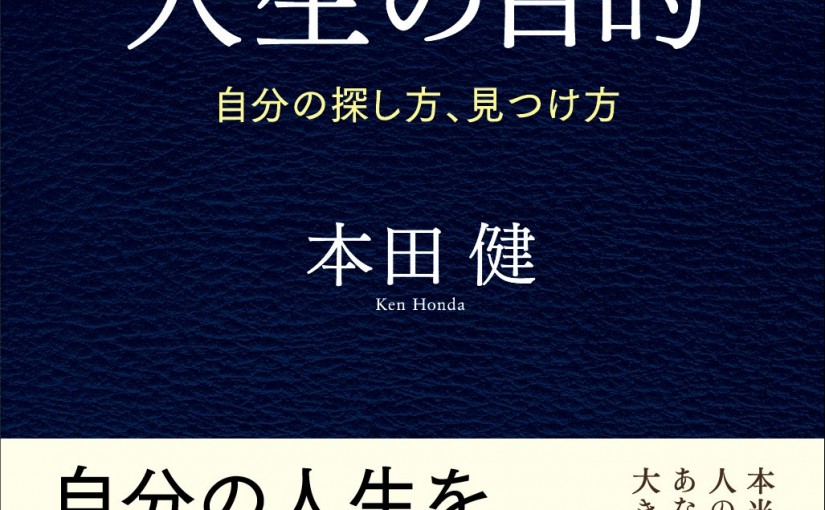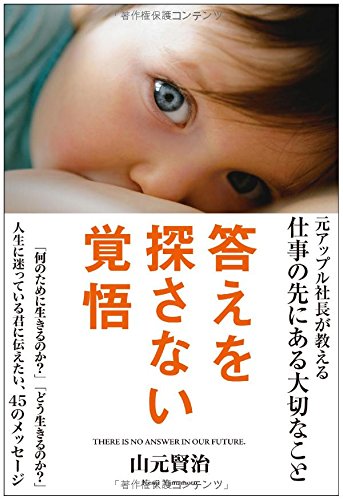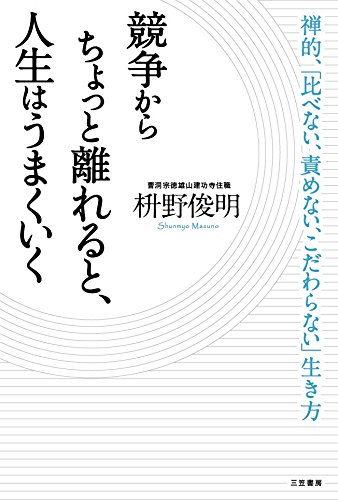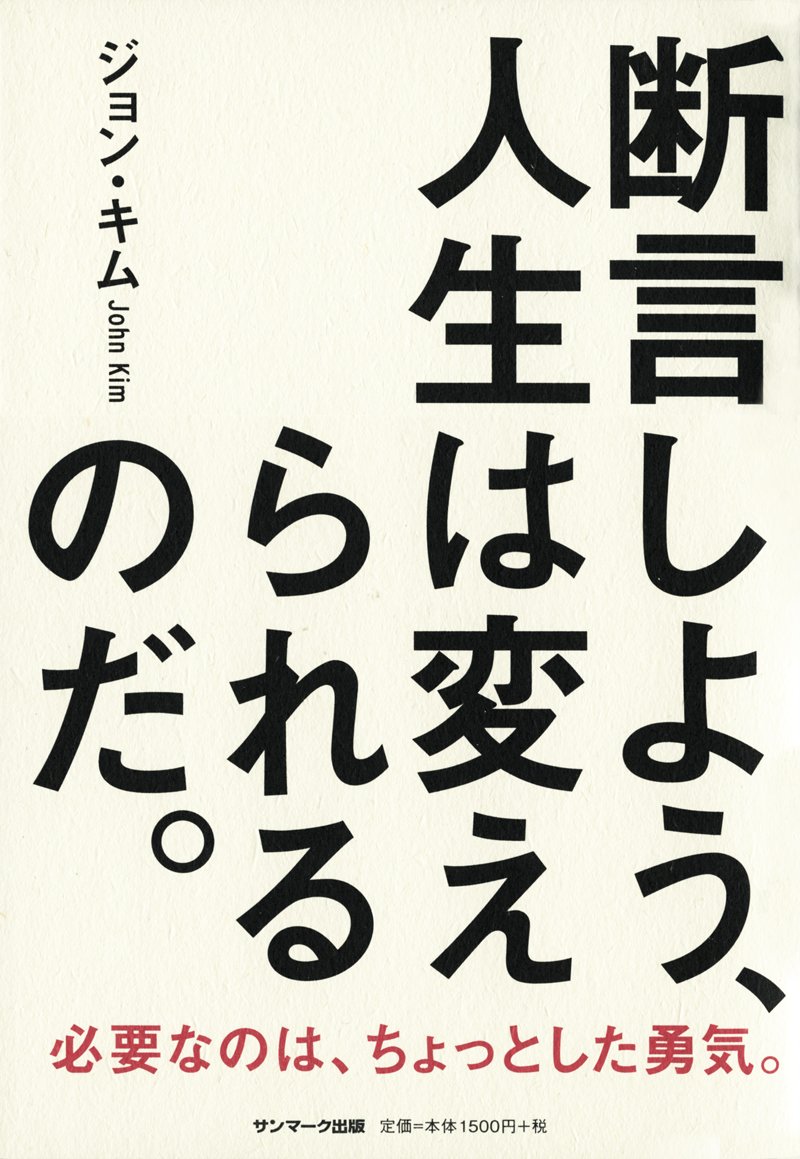意識を向けたものが手に入る
・人生では、その人の意識が向いたものが手に入るようになっています。
・もしも、お金を大事にしているつもりなのに、お金が入ってこないという人は、「大事にする」対象を間違えている可能性があります。
「お金」ではなく「お金がなくても頑張る自分」を大事にしているのかもしれません。
・誰だって、苦しいことやつらいことを経験したくはありません。
それなのに、なぜか「苦しいこと」を引き寄せてしまうのは、知らず知らずに、苦しいことこそが人生だと信じてしまっているからです。
「人生の意味」をどう見つけるのか
・人生には意味があるはずだと考える人は多くいますが、それが苦しみの原因になることもあります。
・いっそのこと、「人生には意味があるようで、意味がない」と考えてみるのも、一つです。なぜかと言うと、動物として人間を見たとき、一生は、「命をもらって、そして受け継ぐだけ」という側面もあるからです。
・あなたが「意味を感じる」ものを探せば、人生に意義を見出せるかもしれません。多くの人は、誰かを愛したり、誰かに愛されたりすることで、自分の人生の意味を見出します。
・あなた自身が「これは意味がある」と思えることでいいわけです。
それが、どんなに地味で目立たなくても、あなたがこれをやるために生まれてきたと感じる活動をやっていれば、心から充足する日々が送れます。
社会的な価値から脱する
・人生の意味を見出すためには、自分なりの価値観をもつことが必要です。
・たとえ世間がどう言おうと、あなたにとって大切なことを一番にしていかないと、人生の意味を見出すのは難しくなります。
・何が正しくて、何が間違っているのか。何が好ましくて、何が好ましくないのか。そういうことを一つ一つ整理していくことが、あなたの幸せにつながっていきます。
「いいか、悪いか」で判断しない
・私たちは物事をつい「いい」「悪い」で判断しがちです。けれども、ある時点では「いいこと」が別の時点では悪いことになったり、ある時点では「悪いこと」が、また別の時点でよくなったりすることはよくあります。
・簡単に「これがいい」「これが悪い」ということを考えずに、「これはいいかもしれないし、悪いかもしれない」「これは悪いかもしれないし、いいかもしれない」というニュートラルな状態でいなければ、人生の本質は見えてきません。
・何かを判断するとき、自分にとって絶対はずせない基準をもっておくことです。直観で決めるか、世間的に有利かどうかで決めるかでは、まったく違った決断になるでしょう。
・忘れてはいけないのは、誰かの判断で決めようとしないこと。自分の物差しをもつことです。
まとめ
人生では意識を向けたものが手に入るようになっている。
37年の人生を生きてきた僕は自分の求めてきたものを手に入れていると実感できる。
たとえば安定した仕事に就き、自分の家族をつくること。
逆に言えば、それ以上でもそれ以下でもない。
自分が大金持ちでもなければ、貧しさに苦しんでいるわけでもないのは過去の自分が安定した中流の平凡な暮らしを志向していた結果なのだと思う。
求めるものがもっと豊かなものであれば、もっと豊かな暮らしを得ていたのだと感じる。
僕が中流の家庭で中流の親に育てられ、それが正しいことだと思っていた。
つまり、そういう思考しかできない土壌で育ったのだと思う。
決して、だから不幸だと言っているのではない。
僕は十分幸せを感じている。
最近、SNSを通して過去の自分のお付き合いの枠を超えた方々と交流することが多く自分自身のそういったブロックも外れつつある。
自分の軸を保ちながらも、自分の外枠を広げていくことで人生の面白さをもっともっと味わえるのではないかと感じているのだ。
そういう風に社会的な価値や常識から判断しない見方で、人生を見つめ直すとこれからの半生はもっとワクワクしたものになるのではないかと期待に胸が躍るのです。