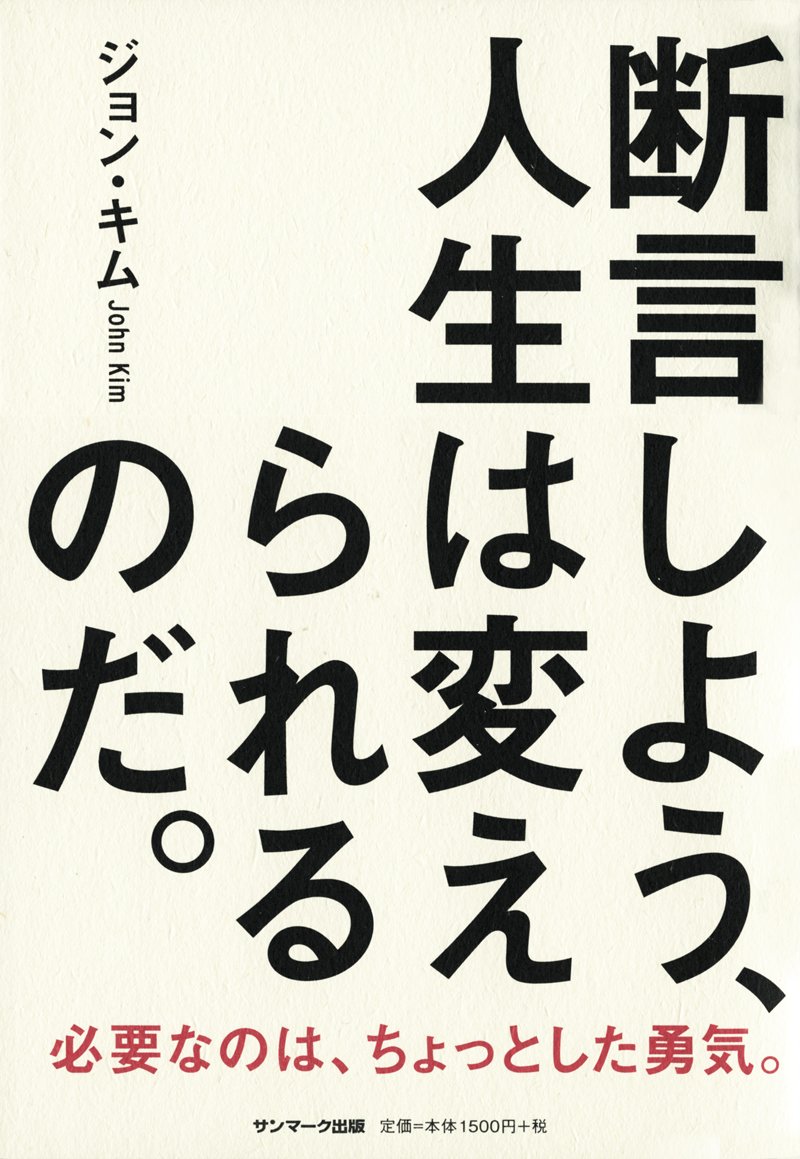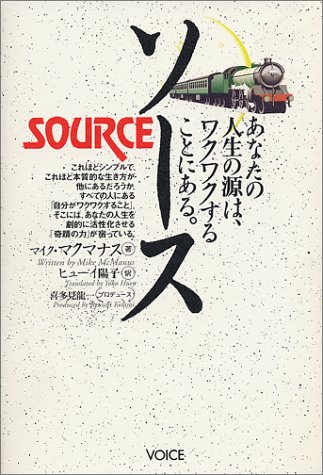人生は時間の使い方でつくられている
・時間をどうマネジメントするのか。
それはすなわち、命をどうマネジメントするのか、ということである。
・時間の使い方は、単なるテクニックだけを学んでも意味はない。
時間によって人生がつくられているのだという感覚を持つことが、何より重要だ。
・自分が何に時間を割いているのか、何に時間を奪われているのかを徹底的に意識しなくてはならない。
人生を短くしているのは、自分自身である
・人生には限りがある、という終わりを意識することだ。
そうすることによって、瞬間を生きる意味が、初めて生まれてくる。
・終わりに向かっていくという意識が、人生のあらゆる時間にかけがえのない意味を与えてくれるのだ。
理想の時間の使い方を徹底的に意識する
・何をするかではなく、どんな心構えで時間を過ごしているか、ということが重要なのだ。
・何が必要な時間で、何が必要でない時間なのかを見極めるには、
自分の人生の中で何がいちばん大切なのかという判断基準を持つことが必要だ。
大事な二割を見極め、まず考える時間をつくる
・仕事ができる人は、本当に重要なことに自分の八割、九割の集中力と時間を使っている。
そして、仕事をスタートさせる前に、その見極めをしている。
とにかく頑張ればいい、ではなく、どこを頑張るのか、を最初に考えている。
・大事なのは問題の定義なのだ。
この仕事においては何が大切なのか、ということを考える時間をつくること。
・自分の時間を配分するということは、自分の命を配分することと同じだ、と強烈に意識する。
やめる、捨てる、断る、離れる勇気を持つ
・自分の命を守るために、また、大切にするためには、ある種の勇気が必要になる。
それは、自由に対するリスペクトから生まれる勇気である。
・やめることを躊躇しない。それが大切だ。
すべての、どうでもいいことに、もう時間を使わない、という決意。
・何でも頑張ればいいわけではない。
頑張るに値するかどうかを、まずは自分の中で見極めることが必要である。
「忙しい」という言葉を使うのは悲しい
・とにかくやってみたいと思ったことは、小さな一歩でもいいので、まずスタートしてみる。
・人生を変えるというと、何か大きなことをしなくてはいけないような気がしてくるかもしれないが、
大事なのは、ちょっとした新しいことを始めてみることなのだ。
・忙しいという言葉は使わないことだ。
それは、自分の器が小さいことの証明でもある。
・全ての瞬間は自分の選択の産物としてある、という意識で時間を使うことが大切である。
まとめ
自分の中で時間の有限性についての意識が高まっている。
「忙しさ」というものが押し寄せてくると、それに抗おうとしても耐えきれず流されてしまう。
自分自身でやること、やめることに明確な判断基準を持つこと。
それによって主体的に時間をコントロールできる。
必然的に死に向かって刻々と過ぎる時間に対して、
追われながら流されていく人生を歩むのか。
自分自身が主体的に時間を支配し、ワクワクすることに時間をつぎ込むのか。
全ては自分自身の選択次第なのだと肝に銘じたい。