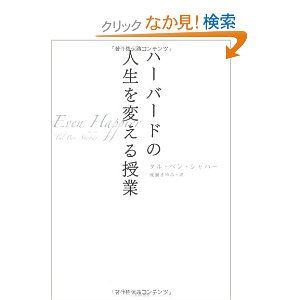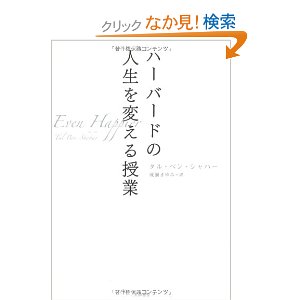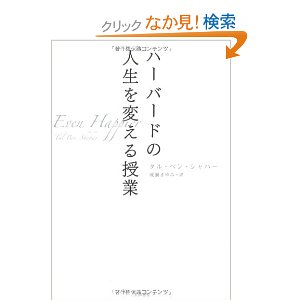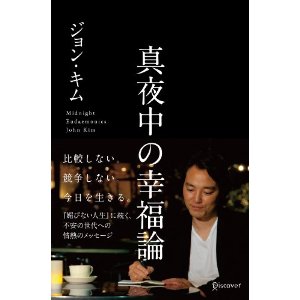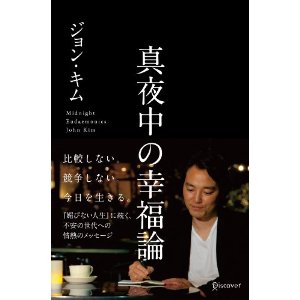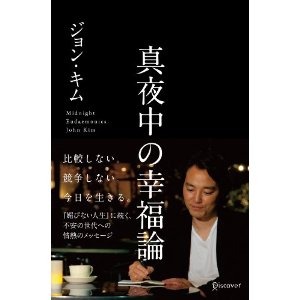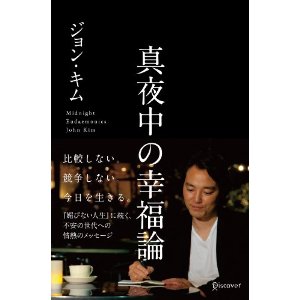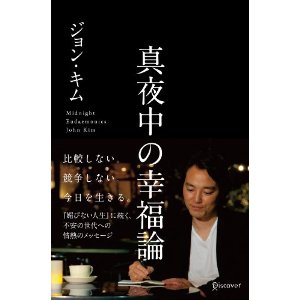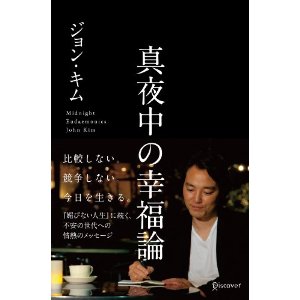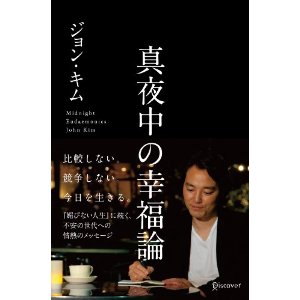●最高の瞬間をつかむ
・自分が何者で、これから何をしようとしているのかという洞察と、将来の困難を切り抜けるための勇気と自信が生まれる
・ピークエクスペリエンスを3日間にわたり1日15分間書き出す作業をする。
・その時感じた感覚や心の動きに意識を向けながら、もう一度その瞬間にいるかのようにイメージしてみる。
●長期的な関係をつくる
・長期的な関係にはすべて、いつかは「行き詰まり状態」が訪れる。
・行き詰まり状態を、個人的な成長と対人スキル向上のための重要な分岐点とする。
●親切な行動をする
・親切な行動以上に「利己的」な行動はない。
・周りの人と多くのものを分かち合い、他の人生に貢献すること以上に満足感を得られる行為はない。
●いいところを探す
・幸福というものは人生における客観的な出来事で決まるのではなく、出来事をどのように解釈するかという主観的な心の働きによって決まるもの。
・最高の出来事が起こるのではない。起こった出来事を最高のものにすることができる人がいる。
・今までの人生の出来事を、始めは「あらさがしの名人」として、次は「いいこと探しの名人」として書き出してみましょう。
●「ありがとう」を言う
・お世話になった人に感謝の気持ちを表す手紙を書き、その人を訪問して手紙を読み上げる。
・感謝の力は計り知れない。
・その人がしてくれたことを具体的に上げて、どういう風に感じ、どういう風に感謝しているかを書いてください。
●回復する
・自然の要求を無視して体と心を酷使し続ければ、個人としても社会としてもその代償を支払うことになる。
・定期的に休息し回復する時間をとるだけで、精神科でもらう薬と同じような効果があるのです。
・最高の自分を引き出すには具体的に何をすればいいかを考え、書き出す。
●パートナーシップを築く
・実際は、いざこざは避けられないものであるだけでなく、長期にわたる良好な関係にとって非常に重要なものである。
・カップルの関係に衝突がないとしたら、それは二人がお互いに重要な問題や相違に向き合っていないということである。
●解釈を変える
・認知のゆがみがあることがわかったら、その出来事に対する考え方を変え、違ったように感じればよいのです。
・自分が人間であることを許し、起こった出来事とその時に感じた感情をあるがままに認める
●子を育てる
・自信や、失敗から回復する力、人生の意義を知ること、そして対人関係に関する大切なスキルを身につける機会を、子供たちから奪っているかもしれない。
・子供たちに自力で困難に挑戦する機会を与える。
今回の中で私が最も重視することは「親切な行動をする」です。親切な行動は最も利己的な行動だと説かれています。日ごろから親切な行動を心がけていれば、その報酬として幸せという究極の通貨を常に得ることができる。幸福は尽きることのない無限の資源でひとりひとり取り分が決まっているわけではない。だからこころの寛容さを持ち、他人と与え分かち合う生き方をすることは「精神と感情の富」を引き出す最良の方法だそうです。与えたり、貢献することが自分の充実感・満足感・達成感に繋がり、たとえ物理的な見返りがなくても幸福感が得られるということです。1日5つ親切な行動をすると心に決めて、毎日実践すれば幸せという究極の通貨を常に得られると思いますので是非実践してみたいと思いました。